
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 第二部(1)
**********************************
「碧」 〜 あお 〜(第一部)
序章
<私は…テレサ……テレザートの……テレサ…>
科学者だった父が、外宇宙の未知の文明に呼び掛ける時、<私はハール。テレザートのハール…>とかならず繰り返し言っていたのをテレサは無意識に憶えていたのだろう。それは、幼い頃に聞き憶えた、宇宙へのメッセージの作法、とでもいうのだろうか。
不思議な装置でいっぱいの天文台で。父の通信を、その椅子の後ろから肩越しに覗き込みつつ聞いた記憶…。その頃の彼女には、それがはるか彼方の見知らぬ星へのメッセージだとは思いも寄らなかった。ただ、通信の最初と最後に名乗るのは何かとても大事なことのようだと、幼いながらもテレサは理解したのだった。
* * *
<私はテレサ…テレザートの…テレサ。今、私たちの宇宙の平和を脅かす、最大の危機が迫っています。この通信を誰か受け取ったら、…一刻も早く…立ち上がって下さい……>
仄かに蒼い光を発する温かな床に、テレサは跪き祈り続けた。深く透き通った水底を思わせる小さな宮殿内部。床に広がる金色の長い髪が、「祈り」の波長の強弱にかすかに震える……
この「祈り」を送り始めて、数十日が経っていた。今日も、彼らからの返答はない。
テレサの「祈り」は、彼女自身のサイコキネシスによって強力な電波となり外部へ送られていた。もともと、あまり電波状態が良いわけではなかった。この場所は幾重にも人工の壁で塞がれた地下にあり、しかもこの大地自体が空洞惑星の内核であった。かといって<力>をセーブして「祈り」を送らなければ、音声としてはどこへもまともに届かないことは承知している。
それでもできるだけ早く、彼らにこの通信を受け取ってもらわなくてはならなかった。もうすでに、アンドロメダ星雲から銀河系の間にある無数の星々が「彗星」に踏みにじられている…。
数百年に一度の軌道を描いてアンドロメダから銀河系に接近する、巨大な天体、白色彗星。それが恐るべき侵略国家であることを、彼女は父の残したデータベースから知った。 ——あの「彗星」に踏みにじられる運命にある他の惑星に、出来うる限り早くその危機を知らせなくてはならない。今までに、この祈りが届いたはずの星々は、その甲斐なくあの彗星に踏みにじられてしまった。
刃向かう星はすべて蹂躙し、その属国に変えて行く冷酷で惨忍な白色彗星帝国ガトランティス。テレザート文明が健在であれば。…国家間戦争など起こさず、一丸となって立ち向かうことができさえすれば、もしかしたらガトランティスにも打ち勝てたかもしれなかった。…だが、この星の文明は今や無惨な骸を晒すだけの代物に成り下がっている。ここにはもはや、戦うための艦船も武器もなく…人さえもいない。どこかの惑星の人々が「祈り」を受け取っても、自分ができるのはただその危機を伝えることだけ。あの強大な侵略国家に立ち向かうための手助けをすることは実質、できない。
(……あの力は、2度と使わないと…誓ったのだから……)
哀しみに伏せた睫毛が、象牙色の頬に震える影を落とす。
テレサは、自分の通信を受け取るであろう遠い星の誰かに、許しを乞いたいと思った。
——テレザートを終らせたのは、他でもない…この自分だったからだ。

——時は、この星の暦で11年前に遡る。
それはテレサがまだ幼いころの記憶であった。
その日、父ハールと母フリッカに連れられ、一人娘のテレサは不思議な場所へ足を踏み入れた。
「お父様、あれはなあに?」
都市から少し離れた自然保護区にそびえる美しい山の谷間。その奥にある深い鍾乳洞の底に、それはあった。
「テレサ、よくお聞き。あれは<テレザリアム>といって、お前のためのお城だ」
「…テレザリアム?」
お城、と聞いてテレサは顔を輝かせた。
「じゃ、お姫様は、わたし?」
「そうとも」ハールは微笑んだが、その笑顔は妙に強張り、頬に張り付いた。「…あれは、お前のために私が作ったお城だ。どんな時でも、お前を守ってくれる……魔法のお城なのだよ」
父娘の後ろに立つ母フリッカは、きつく両手を握り合わせたまま、俯いて唇を噛んでいる…だが、テレサはそのことには気付きもしなかった。
テレザリアムは、鍾乳洞の最奥にある地底湖の上に、反重力装置を作動させた状態で浮いているのだった。小さなテレサには、それが光る青い林檎のように見えた。
なんて素敵な、リンゴのお城…!
「…さあ、テレサ。私たちを、あのお城へ連れて行ってくれないか?」父は幼い娘にそう言った……本来なら、ボートが必要だ。しかし……
「うん、わかった」
テレサはすぐに、父がどうして欲しいのか察した。——ハールは休みの度に、ピクニックと称して娘を人目のない保護区の山林に連れ出し、いわゆるPKと言われる念動力を操る練習をさせていたからだ。しかも、ここにはもちろん誰もいない……<力>を使ってもいいのだとテレサは察し、にっこりした。
<ボートなしで、湖を渡りましょう。さあ、どうしたらいいでしょうか?>
テレサはふわりと片手をテレザリアムへ差し伸べる。すると……湖の水がゆっくりと二つに割れ、湖底に一本の道が現れたのだ。その能力を改めて目の当たりにしたからか、母フリッカの表情が恐怖と哀しみに歪んだ。
「……よくできたね、…テレサ」
誇らしげに微笑むテレサを、ハールは張り付いた笑顔のまま、ゆっくりと褒める。辛そうにその父娘の様子を見守る母フリッカを尻目に、テレサは父の手をとり軽い足取りで湖底へと一歩踏み出した。3人は二つに割れた奔流の壁の間を、テレザリアムへ向かって歩いて行った。
しばらくは、その「お城」、テレザリアムで親子3人は暮らした。
テレザリアムでの14日間は、テレサにとって、まるで夢のような記憶となった——大好きな父は、毎日のようにたくさんの不思議なお話を聞かせてくれ、普段使うことを禁じられている<力>を存分に使わせてくれた。テレサの自慢の賢く美しい母は、その鈴を転がすような声で彼女にたくさんの歌を歌って聞かせてくれた。母がそのほっそりとした指から奇麗な緑色の石の付いた指輪を外し、それをビロードの小箱に丁寧に仕舞い、大きくなったらつけなさい…きっとあなたに似合うでしょう、と言って渡してくれた時の、天にも昇る気持ちをテレサは今でも覚えている。
だが、14日間が過ぎたその直後……まだたった6つになるかならないかのテレサは、「彼女のためのお城」に独り、幽閉されてしまったのである——。
彼女を独り残して行く前に、父ハールはテレサに膨大な知識を与えた。
その宮殿、<テレザリアム>のデータベースには全宇宙のあらゆる知識、あらゆる情報が詰まっていた——プロテクトシールドが張り巡らされた宮殿内部からは外界との接触はできないが、最先端の通信機器を使えば、居ながらにして外の世界をくまなく知ることができる。そしてさらに、年に一度テレサの誕生日に起動する情報ファイルからは、彼女が自分の年齢に応じて知りたいこと・知るべきことをすべて入手できるようになっていた。
しかし当然、まだ幼かったテレサには、なぜ自分がここに幽閉されなくてはならないのか、それが理解できなかった。
「お父様、お母様!…どうして?!」
自分ひとりを宮殿内に閉じ込め、遠離ろうとする父と母。テレサはPKを使って二人に追いすがろうとしたが、それはかなわなかった。
サイコプロテクトシールドは彼女の身体の自由を奪い、テレザリアムから外への出口は固く閉ざされた。テレサはあまりのことに怯え、泣きじゃくる……「お願い、わたしを置いて行かないで…!!」
一体どうして…?!お父様…!!
父は、湖岸で一瞬だけ立ち止まり、テレザリアムを振り向いた。
<………愛しいテレサ。許してくれ……これは、お前を守るためなのだ。…わたしたちは、お前を愛している。…けれど、一緒にいるということばかりが、愛するということではないのだよ。離れていても、私たちはお前を永遠に愛し続ける…>
父は涙を流しながら、俯いてむせび泣く母の肩を抱いて、湖岸から姿を消した。
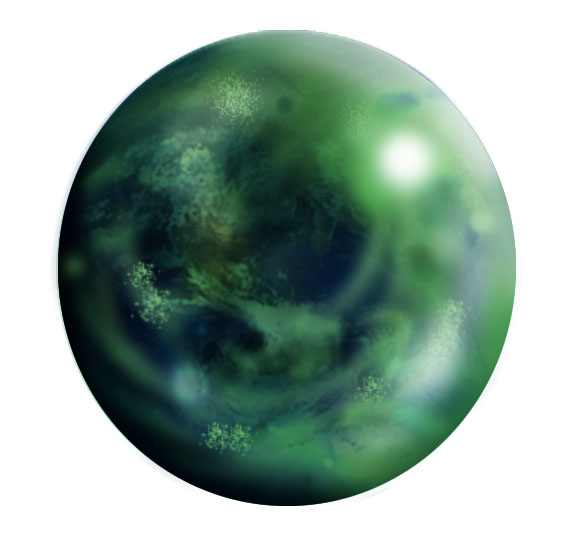
——しばらく後…。
泣き疲れて眠り込んだ幼いテレサを、その宮殿は優しく包み込んだ。 高度な科学力でマシン制御されたテレザリアムは、床や壁、什器と言った硬質の表面部分も適度な温もりと沈み込むような弾性を持つよう設計されていた。また、あるじが嘆いていればそれを慰め、怒っていればそれを宥め…涙が微笑みに変わるよう、空調や超音波が脳波に心地よく働きかける。その思い遣りに満ちた自動ヒーリングプログラムを組んだのは、心理学者としても高名であった母フリッカだった。
とまれ、テレザリアムは実に素晴らしい城だった。——食物はすべてフルオートマティックで栽培され、消費量に応じて常に採取・調理・貯蔵される。父のハールが彼女に与えた知識のすべてはこの宮殿の中に蓄積されていて、いつでも好きな時にテレサの言葉に反応して目に見える形で提供されるようにできていた。
数年後、成長したテレサは反重力バランサーを解除して宮殿ごと移動することもできるようになった……だがそれは、鍾乳洞の中だけ、に止められはしたが。テレサの与り知らぬことではあったが、鍾乳洞の外にはなんと、強固なプロテクトシールドで作られた巨大なゲートが幾重にも設置してあったのだ。まるで、中に恐ろしいものがいるから開けてはいけない、とでも言うように…。