
******************************************
しかしそれでも——。
イスカンダルが黒色艦隊を飲み込んで自爆し、残された古代の兄、守を第一艦橋に迎えたとき。その腕に、愛らしい娘が抱かれているのを見た瞬間。
「それでもあなたには…忘れ形見がいるじゃないか」と不遜にもそんな思いが頭を過った。
俺には何もない。思い出すら、ない…彼女の名を公に呼ぶことさえ、許されていないのに。
——守。悲しまないで…。私たちは、これからも、…いつも一緒です。だって、あなたのそばには私たちの娘、サーシャが——
スターシアにそう言われ、古代守は心なしか微笑んでいたように見えた。
守さんは…確かにスタ—シアさんに愛されているのだ。もう2度と逢えないには違いないが、イスカンダルから守さんを脱出させたのは、紛れもなくスターシアさんの愛情だった…。
古代の言うように、俺の生命を助けたのはテレサの愛の表れだったのだと、何の躊躇いもなく思ってしまえたら。
俺も、少しは楽になれるのかな。
——そんなことも考える。
(……あれは…本当にあったことだったんだろうか)
テレザートのテレサ、彼女の存在と白色彗星…
そんな風にしか思うことも許されない、切ない記憶——。
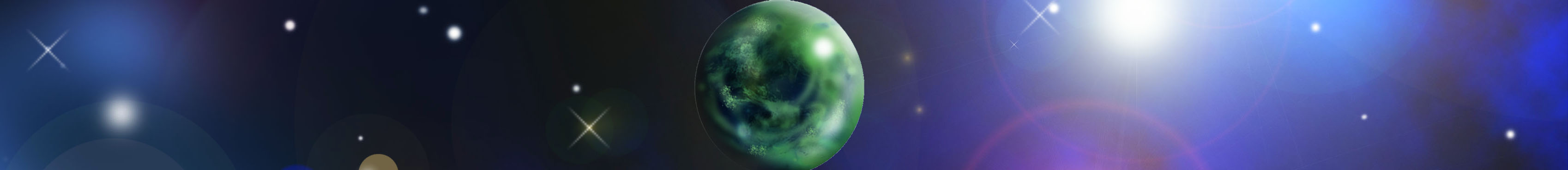
マゼラン星雲からの帰途、思い切って古代守に訊ねた。
「……スターシアさんは、何を考えていたんでしょうか」と。
そんな質問をする以上、当然…端折ってでも自分の身の上に起きたことを、話さないわけにはいかなかった。
淡々と数ヶ月前の出来事を話す島を、古代守は身じろぎもせず黙って見つめていた。
「…俺には、スタ—シアが何を考えていたかなんて……わからんよ」
守はややあって、そうぽつりと言った。わかっていれば、力ずくでも止めたさ。
大事なのは、そんなことじゃないよ、島。
——俺が、スターシアを愛しているかどうか、だ。愛されていたかどうかじゃないさ。そんな答えじゃ、君は不服かもしれんがな。
「君は?その彼女を、愛していたか?」
「……ええ」
それなら問題ないさ。
答えになってませんよ、と言おうとして、守の表情に気付く。
「……すみませんでした」喪ったばかりのあなたに…こんな、無思慮な質問を。
いや、いいよ。
そう言って、守は向き直り、しげしげと島を見た。
「……そうすると、俺も…そのテレサって人に礼を言わなけりゃならないな。島を見染めてくれてありがとうってな。考えてもみろよ、俺たちの還るところがあるのは、…その人のおかげだろうが」
古代さん——
そう呟いた島に、ゆっくりと微笑んで、それきり…古代守は口を閉ざした。
島は、自分ひとりが超常の力を持つ女神に命を救われたことを悔やんでいる。その気持ちはわからなくもない…どんな歴戦の勇者だとて、多くの仲間や部下を失った挙げ句生還するとしたら。それがいかなる理由で迎えた結末であれ「生き恥」だと感じない漢は、いないだろう。だが、女が惚れた男を、例え自分のポリシーに反してでも護りたい…と思うのは、不自然でもなんでもない。守にはそう思えた。島だけのために、テレサという女性が禁を破り大量殺戮に手を染め、命すら投げ打ったとしても、俺は驚かん…女は思いつめると、何をしでかすかわからないからな。
(可愛い女じゃないか)
まったく。何をくよくよしていやがる。それほど愛されたことを、なぜ悔やむんだ。……若いな、島。
(だが、そんな女に惚れられたお前が、それだけいい男に成長していた、ってことか…)
一人微笑み、島の肩をひとつ、叩き。まだ解せないといった顔の彼を後に、守は展望台を出て行ったのだった。

暗くなった海底ドックに、そのまま島は一人、佇んでいた。
(俺も、そのテレサって人にお礼を言わなけりゃならないな)
古代守の言葉が思い出される。
感じ方は、それこそ人それぞれなんだな。だが、誰もが守さんのように思えるわけでもないだろう。現に自分は、徳川太助を新メンバーに迎えたとき後ろめたい気分になった——自分だけが助かって、彼の親父さんを連れて帰れなかったことを、古代以上に申し訳なく感じたのだ。
太助は、当然テレサのことを知らない。だから俺は、知らんぷりしていればいいんだ。なのに…何故か太助に対しては遠慮が先に立ってしまう。彼の親父さんには言えた無茶な注文も、あいつには言えなかった。山崎さんがガンガン間に入ってあいつの尻を叩いてくれたから良かったようなものの。
(そんなことばかり考えていたら、この先身が持たないぞ)と古代にも言われている…それももちろん、真実だった。
『なぜうちの子を連れて帰ってくれなかったんですか』——遺族を訪問する度に、あの戦いの発起人として蜂起を呼び掛けた古代はそう詰め寄られるという……考え込んでいたら、身が持たない。確かにそうなんだろうな…古代。
<うちの子は、私の夫は、私たちの父は。古代さん、あなたの呼び掛けに応えて、出て行ったのに。どうしてあなただけが生き延びているんですか>
100人近い遺族から、古代は今だにそうなじられている、と言った。
彼は、自分自身が沖田艦長に対してそう感じていた過去を持つ。しかし、それも…守さんの生還を境に、また大きく変化しただろう。苦しいのは、俺だけじゃない……
生き延びることを、悔やむ。
死んで行った者たちに、生き存えることを詫びる。
——それは、自然な感情だ。
そして、誰かが死んだからといって、自分や自分の大事な人が生き延びたことを喜んではならないという法はない。
しかし、大勢を引き連れて出た敗軍の将という立場にある場合、こと遺族感情においては…それは許される事ではない。古代の心労は察するに余りある。
「テレサがな、俺に言ったよ。<勝って還るより、負けて還る方が勇気がいることなのですよ>ってな。本当にその通りだ。お前が助けられたことで悩むんじゃないかってことも…ある程度分かっていたんじゃないのかな…あの人は」
それでもお前に、生きて欲しかったんだよ…彼女は。
だからこそ。過去にとらわれるのではなく、明日へ。前に向かって進むしか、ないじゃないか……島。俺も、お前も。
——そう言って、古代はその兄と同じように微笑んだ。
そうだな。お前の言い分はもっともだ。
だが、古代も、古代の兄さんも…悩んでいないわけじゃない。あの二人が心から笑っていないことも、自分は知っている。
——男は虚勢張ってなんぼだからな。俺たちはみんな、天下の強がり、意地っ張りだから。

——突然、人気の失せたドック内に誰かの靴音が響き、島の思索の糸を断つ。
感電を防止するための鋲が靴底に裏打ちされた、重い靴音だ。……機関部の誰かかな?まさかな…
そう思った途端、耳慣れた声がして島は驚いた。
「島さん、あぁまだここに居たんですか!」
「太助か?」
やっと見つけたよ〜…と言いながら、徳川太助が薄暗いコンコースの奥から姿を現した。太助は先ほど担いで持って出たはずの大きなザックをそのまま、床にドサリと置いて朗らかなえびす顔で笑った。
「なんだお前、帰ったんじゃなかったのか」
「いやあはは…、さっきはあいつらと一緒だったもんですから」
「…俺に何か用か」
ええ、まあ。
へへへ、と照れ笑いする太助の丸い額が、その父親を思わせる。
「…これ、島さんに見てもらいたくて、ずっとチャンスを待ってたんですよ。検閲から戻って来たのが出発直前だったもんですから、自分で中を見る暇もなくて」
そう言った太助がザックから取り出したのは、B5程度の大きさのノートだった。
「なんだいそれ」
「航海日誌ですよ」…親父の。
親父の字、へったくそな上に文章支離滅裂で。でも、最後まで読みました。でね。
「俺、島さんに聞きたいことがあるんです」
「聞きたいこと…?」
*************************************
(3)へ