 <(19)
<(19)
……この中に……
一瞬、時が乱暴に巻き戻されたような錯覚に陥る。だが、すぐに島は我に返った。
「道理で…ずっと何か奥歯に物の挟まったような話し方をすると思ってたよ、古代。…これは、受け取れない。…というより」
穏やかな笑顔で覗き込むように見られて、動揺しているのは島ではなく自分の方だと、古代は認めざるを得なかった。川面に反射するイルミネーションに照らされた島の顔は、自分に対する友の思いやりに心から感謝はしていても、狼狽してはいなかった。
「……これはもう、俺には……必要ないものだ」
「島」
「古代。あの時のことは、お前から直に聞いた。それで充分だ。…お前が、これを持っていたくないなら、ここからこのイーストリバーに投げ込んだらいいさ」
「島……」
古代は面食らった。
テレサのセンサーフォトの件を聞いて、雪とも何度も話し合ったのだ。
島は、忘れたいと思っている、と自分で思い込んでいるだけだ。
忘れたと思っている、という自己暗示にかかっているだけだ。
センサーフォトがあんなにも鮮明だったのは、そうとしか判断できない。
……これは真田の意見でもあった。
彼女とのことが、トラウマになっているのなら…トラウマを完全に治療するためには、「その時」に奴の時間を巻き戻し、あれは現実だったと再確認させることが第一歩だ。それをするのは、出来るならこの任務に出る前の方がいい。……せめて、自分がどれほど深く傷ついているか、気付かせなくてはならない……
それなのに、島は……「必要ない」だって?
古代は言うまいと思っていたが仕方なくセンサーフォトの件を切り出そうとした。
「お前、あのさ…」
「いや、…やっぱりもらっておこう。仮にも軍のトップシークレットを川に捨てたりしたら、シャレにならんからな」
古代がやっとの思いで言いかけたその時、思い直したようにさらりと島がそう遮った。
「……なにより友だちの好意は、無駄にするもんじゃないよな。古代、お前……ずっとこれを持っていてくれたんだろ?……悪かった。だから、もう…あの時のことは、忘れてくれ」
俺を、哀れむな。
島の目は、そう言っていた。
「島…」
親友が、朗らかに笑ってさっとチップをケースごと上着のポケットに無造作に突っ込むのを見て、古代は二の句が継げなくなった。
(……こんなんでよかったんだろうか)
今まで何年も、あのメモリチップを見ては溜め息を吐いていた自分が滑稽に思えるほど、簡単に事は済んでしまった。ただ……、受け取ったはいいが、島が記録を再生してみるかどうか、それについては自信が持てない。こんな渡し方で、本当によかったのだろうか…。
「もう一杯飲めよ」
黙っている古代に向かって、島がワインの瓶を突き出した。軽い飲み口の発泡ワインなので、幾らでも飲めてしまう。古代は気を取り直してグラスにワインを受け、自分も瓶を受け取って島のグラスに注いだ。
「そういえば佐渡先生、タダで飲み放題だ、ってはしゃいでたけど、日本酒にありつけたかな」
「でも……会場にはSAKE、なかったかもしれんぞ」
そういえば、会場には気取ったカクテルや洋酒の類いしかおいていなかったようだ。もしかしたら、パーティーには来ないでまたもやヤマトの医務室でネコのミーくんと酒盛りしているのかもしれない。
「あはは、そうかもしれんな」
その光景はあまりにもありありと想像できたので、二人はどちらともなく笑い出した。
(これでいいんだ…)
古代は笑いながら、…笑っている親友を見ながら、島はとてもいい笑顔で笑うようになったな、と心から感じた。
——テレサと出会う前の屈託のない彼に、いつの間にか戻っているような気がして、古代はひとまずホッと胸を撫で下ろしたのだった。
だが、本当のところは……そうではなかった。
この時、島は正直、メモリチップの記録を再生してみるつもりはほとんどなかった。古代の思い詰めた顔を見てしまったので、まずはもう、何も問題はないよ、と安心させてやりたい……その思いだけで、彼はチップを受け取ったのだ。
テレサ一人を犠牲にしてヤマトでおめおめ生きて戻ったと、古代はずっと気に病んでいた。そんなことで悩むなと、何度言ってもだめだった。
テレサのことがトラウマになっているのは、俺じゃなくて実は古代の方なんじゃないか、と島は感じていたのだ。このメモリチップが俺に渡ることで、奴の中で何かが一区切りつくのなら、古代のために受け取っておこう。その上で、再生することは考えても見なかった。
彼女とのことは、自分にとってはもう、丁重に葬った「過去」なのだ。
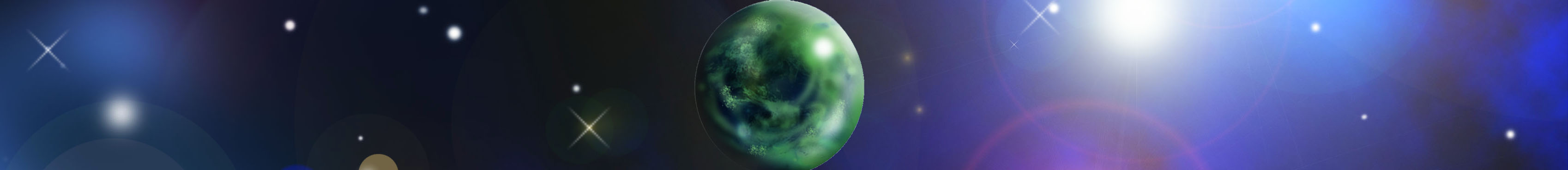
両親が藤堂の宿泊するプレジデンシャルスイートに招かれている間、島は古代たちと別れ、次郎と二人でホテルの部屋に戻って来た。
時差ボケでまったく眠気を感じない次郎と対照的に、規則正しい生活を送っていた島はすでに眠くて仕方が無い。カラスの行水程度にシャワーを浴びて、あくびをかみ殺しながらベッドルームへ戻って来ると、次郎がプロジェクタの大画面に向かってベッドの上にちょこんと座り、何かを無言で見ていた。
「何見てるんだ……?次郎…」
パジャマのズボンだけを履き、裸の上半身にかけたタオルで濡れた頭をごしごし拭きつつ画面を見た島は、絶句してしまった。
「おい、次郎…」
「この人なんだね……」
次郎は画面から目を離さずに呟いた。ベッドルームにあつらえられた大画面プロジェクタに映されていたのは、酷く粗い画像ではあるが緑灰色に光る星テレザートと、その手前に投影された蒼いドレスの、美しい女神の祈る姿………。
『わたしは…テレサ。テレザートの……テレサ……』
性能のいいスピーカーから流れる音声は、元の音源が傷ついているためにかなり雑音が多かったが、それでも彼女の声は、天使のように清らかで美しい……
「……次郎、勝手にそんなものを」
そう言いながら、島は画面から目が離せなくなってしまった。画面はヤマトのメインパネルに捉えた交信画像と音声で、途切れ途切れに所々相原の声や自分の声が混ざり、突然脈絡無くぷっつり途切れたりしていた。
次郎がゆっくり振り返って、茫然としている兄を見上げた。
「兄ちゃん、……この人」
「お前には…関係ない」
「テレサ、…なんだろ」
「だから、何でお前が知ってるん……」
そこまで言って、島は我に返る。「そうだ、さっきも言ってたな。ポセイドンにテレサに似た人がいるとかなんとかって」
次郎はこくりとうなずいた。
「さっき、バルコニーのところで会ったんだ……兄ちゃん、おかしいよ?どうしたんだよ、何をそんなに…」
何をそんなに、動揺してるんだよ?
やっぱり兄ちゃんは…この人のことを、まだ……。
すると、兄が突然、次郎の手元にあったリモコンをひったくり、映像を消した。
「どうもしない。この人がテレサだ。…何が知りたい?古代たちに何か言われたのか?」
「そんなに怒らないでよ、兄ちゃん。ごめんよ……」
「怒ってなんか……」
怒るつもりは無かったのに、見れば弟はうなだれて謝っていた。「別に冷やかそうとか、からかおうとか思ったわけじゃないよ。前に兄ちゃんが持ってた写真の女の人……、名前も、誰なのかも教えてくれなかったじゃん。だから、雪さんたちに聞いたんだよ、この人は誰?って。そんでさ、さっきあれが兄ちゃんの服のポケットに入ってたからさ……」
——服のポケット。
ああ、そうか……。
次郎がもっとずっと小さい頃。勤務から帰って来るたびポケットに飴やガムを入れておいて、探させる遊びをしてやったことを思い出す。兄ちゃんのポケットは魔法のポッケだね、と顔を輝かせてまとわりつく次郎が可愛くて、あれこれと趣向を凝らしては小さなお土産を持ち帰ったものだった。
次郎が中学生になって以降は流石にその回数は減ったが、防衛軍本部や真田のラボでお茶うけに出されたお菓子だのバレンタインでもらう義理チョコだのは、ポケットに入れておくと次郎が勝手に戦利品として持って行っていたようだ。時にはそれが次郎お気に入りの人気アーティストの、ニューシングルメモリディスクだったりした…だから、次郎はその感覚で兄の上着のポケットを探ってみたのだろう……そして見つけたのが、このチップだったのだ。
しょうがないなあ…と溜め息を一つついて、島は取り上げたリモコンをベッドの上にポンと投げた。
「……お前も、もう15だもんな。好きな子のひとりくらいはいるか…」
部屋が暗いのが幸いだった。こんな話、照れくさくて明るい部屋の中でなんかお互いできるわけがない。
「……うん……まあね」
「じゃあ、察してくれよ。……俺は、この人が好きだったんだ。彼女の方でも、俺のことを…。でも、…彼女は、俺が負傷して意識がない間に地球を守って死んでしまった。そのメモリチップは、古代がさっきくれたんだ」
「…………」
相原がきっちりと残していた通信記録に、兄の楽しそうな声、相手のテレサという女性を呼ぶ時の嬉しそうな声が残っていた。
「彼女は、白色彗星帝国が地球に向かっていることを伝えてくれた……ここまでは知っているよな?」
「うん」
「俺はヤマトの通信を通して、彼女と仲良くなったんだ」
「うん、兄ちゃん、楽しそうだったよ」
「ちぇ。…くだらない記録まで残してるんだな」
苦笑いして舌打ちする。
「ただ、彼女の件は今、防衛軍の第一級重要機密になってるんだ……外では絶対に口にしないと約束してくれなきゃ、これ以上は見せられないぞ」
「わかったよ」
本来は、古代が持っていたこのメモリチップの記録は極秘資料であり、持ち出しは厳重に禁止されているはずの代物だ。だが、ブラックボックスの回収を担った真田と解析を任された相原は、躊躇うことなく資料のコピーを作った。彼らは是が非でも島のために、「彼女」の遺影を残してやりたかったのだ。おそらく本部に保管されているブラックボックスのオリジナルデータは、これよりもずっと不鮮明だろう、と古代は言っていた。
次郎がもう一度画像の再生を始めた。ヤマトはテレザート星に到達し、上陸部隊が降下したらしい。斎藤の解説付きでテレザートの巨大な都市の廃墟の様子が画像で送られて来ていた。
そして…途切れ途切れの音声と画像が続くうち、いきなり画像は途切れ、音声に大きなノイズが混じり、……その後、唐突に美しい声が流れ出した。
『……島さん……会いたい。……もう一度……。もう一度……会いたい、島さん……』
その切なく甘えるような声に、次郎は急に頬が火照るような気がした。
「島さん」…次郎だって「島さん」なのだが、この声がもう一度会いたいと哀願しているのは、他ならぬ自分の兄なのだ。もしも自分が、こんな声の、あんなに美しい人からこんな風に言われたら、…もう……。
——と、勝手にそう照れながらベッドサイドに立っている兄の方を見る。
がしかし。
兄の方は、画面を見ていなかった。
郷愁に浸るでもなく感慨深く何かを思うでもなく、……眉間にしわを寄せてまるで怒ったように床を見つめ…
「兄ちゃん……」
呼びかけても、兄は黙ったままだ。
大介の中では、急速に時間が逆行していた。この声に引き寄せられるようにテレザート星に向かった自分は……彼女を、この胸に抱いて……そして……
「……くそっ…」
食いしばった歯の間から、嗚咽が漏れた。
次郎は急にいたたまれない気持ちになった。興味本位で根掘り葉掘り聞き出したはいいが、この出来事は兄にとってはいまだに……、いい昔話、で片付けられるものではないのだと唐突に悟ったのだ。
「兄ちゃん、……俺…」
次郎はリモコンをぐっと握って、ディスクの停止ボタンを押した。
「ごめん、兄ちゃん。…ごめん」
「次郎…」
大介がはっと気付いた時には、次郎は身軽にベッドから飛びおりて、奥の自分の部屋へ駆け込んでいた。
「……次郎!」
(21)へ