*************************************
「…次郎、身体に気をつけるのよ」
「わかってるよ…」母さんったら。そんなに遠くへ行くわけじゃないんだぜ?セントラルコーストの科学局官舎なんだから、学校の寄宿舎へ入るのとそう変わらないだろ?
「そうね、それは…そうだけど」
あなたを手放したくはなかった、…母がそう思っているのは手に取るように分かる。ずっと自宅通勤だった。こんな歳まで親元にいるのは完璧なマザコンだと、苦笑することも度々。自分の姿に、長兄の面影を探す母…10代の頃は、それが悔しくて兄を恨んだこともある。俺は次郎だ、兄貴じゃないんだ。だが、時が経つうちに兄との約束を再び思い返した……「父さん母さんを、頼んだぞ」
それは、傍にいることのできない兄自身が次郎に託した、両親への思慕の情でもあったのだ。
自分は兄に、約束したのではなかったか。「任せとけよ!」と。
母が、父が、兄に思いを託すように自分へもその思いを託すのを温かく感じ…次郎は自身、それに応えようと思うことができるようになった。
そして、この日。
父母と暮らした家を、自分はついに…後にする。
「…科学局とはいえ、お前の立場は複雑なんだから。いざこざに巻き込まれないよう、充分気をつけるんだぞ。私からは、…それだけだ」
父の言葉に、うん、と頷いた。
「行って参ります」
つい、兄がよくそうしていたように「敬礼」しそうになる。苦笑して、次郎は荷物を手に持ち、挙げた手をそのままさっと振った。
科学局からの迎えの車が玄関のエントランスに待機している……
「行ってらっしゃい、…次郎」
次郎。
そう母はもう一度呟いて、彼を見送った。
***
——古代さんが、軍を離れた……それを聞いた1週間前にはまだ、次郎の決心は揺らいでいた。
『開拓省から連邦科学局へ暫定的に移籍し、私の仕事を手伝ってはもらえまいか』
そう真田長官から打診されたのと、古代進の退役と言うショッキングなニュースはほとんど同時で、次郎は即座に返答が出来ずにいたのだ。
この1週間、次郎は逡巡し続けた。宇宙戦士にはならない、と誓った自分だが、真田の元で働くとすれば何が起こるかわからない。真田自身が、科学局長官という身分であるにも関わらず度々外宇宙の戦いの旅へ出て行ってしまうのは、有名な事実である…。
それだけではない。真田の元で与えられる仕事次第では、自分が今粉骨砕身している大切な仕事も中途半端に放り出すことになる。それだけは我慢ならなかった。
科学局で協力するにしろ、自分の計画の妨げになるようであれば協力自体しかねる、と思う。それは、宇宙開拓省移民局長として彼の中で構築している大事なパズルの一片——人類の存続をかけて移住できる文明惑星を探索することと移住に関する直接交渉、だったからだ。それを放り出して別のプロジェクトに邁進するつもりは、まったくなかった。
科学局への移籍は、現段階ではあくまでも自分の描くその壮大なプロジェクトの遂行にとって、プラスになるからに過ぎない。
しかし正直な所、開拓省の官僚の中には次郎の危惧を鼻で笑う連中もいるのだった。
「この平和な時代に、異星人の来襲だの、銀河規模の災害だのと、一体あの若造はなにを心配しているんだね。どこからも襲撃を受ける可能性などないのに、万が一の移住先を確保するのだと?そんな無駄な経費を使うくらいなら、我々の年棒を上げてほしいものだ」
かつて太陽の膨張によって地球が滅亡の危機に晒されたのも、結局ガルマン・ガミラスと他の銀河の異星人たちのいざこざに巻き込まれただけの、いわばとばっちり、だったではないか。今や、そのガミラスも我々にとっては戦うべき相手ではない…水惑星の接近や地球人の祖先だと言う宇宙人の来襲も、もはや過去のものだ。『宇宙移民』は確かに、万が一の策として残しておくべき物かもしれぬ、それゆえ移民局と言う省庁は存続している。だが、それが果たして来たのはこの10年、過去のデータの編纂と、毎年の最低予算の消化だけではないか…?
現在移住先として探査対象になっているのは、かつての移住用艦艇の限界航続距離である1万5千光年を超えてさらに伸び、地球から約3万光年までの範囲。次郎が局長を務める移民局は、その母体本部である宇宙開拓省から疎まれながらも宇宙商船大学の協力を得て細々と探査を行い、現在その候補地として幾つかの惑星を発見し、順次交渉へと計画を推移している段階であった。
真田に声を掛けられたのは、その最中のことだったのだ——。
(…真田長官が手伝って欲しいと言うのは、一体どんな仕事なんだろう)
迎えの車の中で、通り過ぎて行くメガロポリスの街角を見ながら…思案する。
噂では、各省庁・企業・各種学校から優秀な人材が水面下で集められ、極秘計画を遂行するための特殊機構が形成されているらしい。もとより、「科学局長官・真田志郎」と言えば、天才と名高い反面「変人」という浮き名を流すことでも有名だ。汚職がらみで衰退した防衛軍に成り代わり、事実上各国の軍備を代理統率するほどの権限を有した科学局とはいえ、その長である真田志郎の正体を知る者は実は非常に少ないのだった。
(古代さんが家を出て行ったのと、何か関係があるんだろうか…)
次郎は、古代の娘を思い浮かべた。父親譲りの抜群な運動神経に恵まれた、利発で賢い愛らしい少女。パッと見はまるで親子に見えない二人だが、次郎はあの二人の共通点が古代の滅多に見せることのない「富士額」だということを知っている、数少ない者の一人だった。
それにつけても、不憫なのは美雪ちゃんだ。雪さんはもちろん、古代さんが軍を離れた理由を知っている。美雪ちゃんは賢いから、きっとある程度事情を理解しているだろうが、事実上は父親が家を出て行方を暗ましてしまったのと変わらない…。自分は父親に捨てられたのだ、などと思っていなければいいのだが。
自分も詳しく説明されたわけではなかったが、連日報道される汚職疑惑、資源開発に関する対立と抗争のニュースを見ていれば事情は大体解った。命を賭けて共に地球を守った仲間同士でそんな修羅場になっていれば、誰だって。その上、古代さんには対立グループ双方からの圧力までかかっていた。いたたまれなくなるのは、当然だ。
古代進からの短い連絡を、次郎ももらっていた。
<君は…時代に押しつぶされるなよ。色んなことを乗り越えて来た君だ。きっと大丈夫さ>
古代さん。何が大丈夫なんですか…?
参ったな。古代さんの言葉足らずは毎度のことだが、残念ながら俺は…兄貴じゃない。古代さんの真意を汲み取る能力は、兄貴ほど高くないんだがな…。
その短い電信を受け取った時、次郎はただ苦笑するしかなかった。ただ、次郎へのそのメッセージを届けに来た雪は、穏やかな顔をしていた…だから次郎も、「どうして」だとか「なぜ」だとかは…訊かなかったのだった。
古代進は地球から逃げたのだ、と公然と罵る輩もいた。だが、次郎には分かる。
(そうじゃない…古代さんは自分一人が非難を受けることで、その矛先を雪さんや美雪ちゃんから逸らしているんだ。いや、それだけじゃない…ヤマトで共に闘って来た他の仲間たちの名誉も…、そしてヤマトそのものの名誉も、護ろうとしてくれている)
物故した上官たち、そして英雄の丘に眠る仲間たちに対しても——決して非難が及ぶことのないように。古代の行動の裏にあるその精神を理解した時。次郎も決断したのである、当座は真田の思惑に嵌ってみよう、と。
ただ…、心の片隅に僅かに浮かんだ疑念がひとつ。
(……真田さんは、俺が…兄貴の弟だから、という理由で呼び寄せようとしているんじゃないだろうな)
<兄の七光り。誰のおかげで優遇されてると思ってる?思い上がるな、縁故で入省したくせに。お前は所詮、開拓省の客寄せパンダなんだよ…島大介の弟くん>
妬みと羨望から発せられるそんな事実無根の中傷など、次郎は今では歯牙にもかけない…この手の悪口は、学生時代から嫌というほど浴びせられて来た。だが、世界最高水準を誇る地球連邦大学に一般入試でトップ合格して以来、そんな気の毒な讒言など相手にしなくてもいいと心底感じるようになったのだ。言いたいだけ言っていろ。悪いが俺は、とっくに兄貴を超越したんだ。
しかし。
縁故、というよりも。同情だとか、兄貴に由来する単なる仲間意識で俺を呼び寄せようとしているのなら。——例え天下の科学局長官の要請だろうと、俺はそれを蹴って移民局に戻るかもしれない、と次郎は思うのだった。
***
「遅くなりました。…島次郎です」
「良く来たな。…まあ、入りたまえ」
地球連邦宇宙科学局・長官室……に招かれると思っていた次郎は、通された部屋の様子に面食らっていた。
その薄暗い部屋には、新品の電子機器独特の匂いが漂っている。新開発の機器のテストでもしているのだろうか…?
部屋の規模は、平均的な作戦司令室と同等の広さだろうと思われた。スポットライトで照らされた、今立っている空間の一段下にさらに広い空間が広がっており…そこに無数のコンピューターの気配がある。次郎をここまで誘導して来た女子学生が、退室するわけでもなくそのまま真田の横に姿勢を正して待機する。身のこなしからすると、彼女はおそらく軍人…いや、訓練学校の生徒だろう。やはり…この極秘計画のスタッフなのだろうか。
「……久しぶりだな」
「はい、ご無沙汰しておりました」
真田志郎はそのいかつい眼差しをふ、と和ませ。おもむろに次郎の差し出した手を取って握った。
ここはなんですか、と聞きたい気持ちを抑え、次郎は真田の次の言葉を待つ。
「折原くん、あれを」
「はい」
折原くん、と呼ばれたその女子学生が、黒い表紙の分厚い書籍を真田に手渡す。……ん?あれは?
「……君の書いた研究論文だよ」
「え?」
さらに真田からそれを手渡され、きょとんとした。折原が、こちらをまん丸な目で見つめている。興味津々、といった顔だ。…苦手だな。天才肌の子は、どうも視線に遠慮ってものがない…。しかし。
「なぜこれを?しかもこれは、卒論ではなくて…在学中に書いた……」
「単刀直入に言おう。私は君の、その論文を読んで、君をここへ招きたいと思ったんだ」
いよいよ訳が分からない。真田は戸惑う次郎を見てにやりと笑った。
「折原くん」
はい、と頷き、彼女は薄暗い部屋の下段に降りて行き、部屋の照明、そして室内に並ぶモニタを一斉に稼働させた。思った通り、この部屋は明らかにCDC、作戦指揮所の様相を呈している。だが、…なぜ?
「…これは……」
「ここが、宇宙科学局、Y計画作戦司令室だ」
作戦…司令室??科学局の…?!「ワ…ワイ計画…?」
いつの間にかそばに戻って来ていた折原が、「うふふ」と笑った。「カッコ悪い名前ですよね〜」真田長官、そういうネーミングのセンスはゼロなんですよ。
「は、はあ…」
呆気にとられる。作戦司令室、って。防衛軍でもないのに…?
思ったより高い場所にあるこの空間はおそらく発令所、いわゆるコマンダー・ブースだ。下段に並ぶ数十基のモニタは、見る限り最新型の大容量スーパーコンピューターの画面。そして、眼前には巨大な3面式ホログラムスクリーン……
「知っての通り、今…防衛軍本部はほとんど機能していない。統率する者がいないのだ。相原も南部も…色々と悪い噂を聞くが、彼らにとっても本意ではなかろう。太田のように古代と同様、身を隠した者もいる…。そんな状態で現実に地球が今危機を迎えたら、我々は滅びるしか無くなってしまう」
発令所の先端、下段にコンピューター群を見下ろす位置に歩を進め、真田はおもむろに呟いた。
「…ヤマトのない地球、今やヤマトという『希望』を失った我々に、地球を守るためにできることは何か。君がその研究論文で描き出したビジョンは、私とまったく同じものだったんだ、次郎くん」
思わず、手にした黒表紙の本を見る。
「……しかし、地球が滅亡の危機を迎える可能性は低いです。大学でも教授の半数が…、今僕のいる開拓省でもほとんどの官僚が否定的です」
「それでも君は、備えようとしている。違うか」
それはもちろんです……言わずもがなですが。
兄たちの護って来た地球だ。万が一の危機を迎えた時点で打つ手がない、などということは決して許されません。
真顔でそう言った次郎に、真田は満足そうに頷いた。
「君が責任者としてその計画を進めているそうだな。宇宙商船大学の協力を取り付けて、移住に関する交渉を進めている惑星は今、幾つある?」
「……今のところ、サイラム恒星系のアマール、クラビーク太陽系第4惑星ルーンの2つです。ですが、ルーンは大気組成に多少問題があり、さらに領土の関係で受入れに対しての交渉が少々難航気味で」
真田はそれを聞きながら、ゆっくりと微笑んだ。「…アマールの場合は、その衛星を提供すると言われているのではないかね」
「………長官」
「見返りは、…技術提供。再生プラント輸出、波動エンジン他、軍事関連技術の輸出」
なぜそれを!?
「申し訳ない、次郎くん。君のその論文に出会って以降、我々はそれを指南書に、君に先んじて計画実現に向けて邁進して来た……」
わかるか?キミのアイデアを横取りしたんだ。
仰天し、ただ呆気にとられる次郎にさらに真田は続けて言った……
「すまん。訴えられても致し方ない」両手を拡げ、大袈裟にこちらを振り向く。「……計画を立てたご本人を差し置いて、こんな作戦本部を作ったり人員を集めたりしていた。まったくもって、出過ぎた真似をしているんだ……勘弁してくれるか」
開いた口が塞がらない、とはこのことだ。ややあって、次郎は…「は、」と息を吐き。
「……僕は、…てっきり…。兄さんの七光りで僕を真田長官が呼んでくださったのかとばかり」
「私を見損なってもらっては困るな」
真田はフン、と鼻を鳴らすと腕組みをした。「その論文が君の書いたものでなければ、私は君をここへ呼んだりはしないよ」——例え、島大介の弟であろうともな。
「……!」
申し訳ありません、と頭を下げつつ、次郎は満面に広がる笑みを押さえきれなかった。これまで、酷評を受けつつ細々とやってきた自分の計画を、この科学局が、真田長官が…最新の設備と天才集団を率いて、引き継いでくれるっていうのか!
「しかし、なぜこの時期に…と思うだろう?」
次郎がその疑問を口に出そうとしたと同時に、真田がそう言った。
「折原くん」
感無量の思いで頭を上げた次郎の目に、突然大スクリーンの映像が飛び込んで来る。
「Just in case…そう思って君は今まで、その計画を遂行して来たのだと思うが」
皮肉なことに、ついに…来てしまったんだよ、その「時」が。
えっ……?
大スクリーンには、銀河系中心部のモデリング画像が投影されていた。天の川銀河の中心部、地球から約3万光年の距離にある密度、重力が無限大の特異点……
「これは」
「…ブラックホールだ」それも、観測史上最大のブラックホール。「これは最近になって観測されたものではない。あの場所に、何万年も前からあったものだ。だが……この数ヶ月、異常が観測されている」
「異常?」
「……地球へ向かって、移動し始めているのだよ」
「なんですって……?」
折原が続けて投影した左右のスクリーン映像に、次郎は息を飲む。銀河中心部から派生したブラックホールの触手、とも言うべき次元の歪みが、明らかにこの太陽系を目指して移動しているのだ。
「どうして……」
白色彗星のような、人為的な物なのではありませんか?!
「その可能性も捨て切れん。だが、今のところそれを匂わせる動きはない。自然現象であれば途中で進路を変える可能性もあるが…」
「…現在、あの移動性ブラックホールの速度は毎秒15,000キロほどです。規模はまだ、把握できません。ですが超大型だということだけは…確実です」
モニタを操作している折原が、改めて地獄の使者を見た、とでもいうようにそう呟いた。
「毎秒15,000キロ」
「……私の計算では、これがこのまま直進してくれば…間違いなくまた」
「人類は…滅亡の危機に晒されると」
「…そうだ」
一両日中に、私はこれを連邦政府議会に諮るつもりだ。全世界の宇宙天体物理学の権威を総動員し、対策を練る。…君の論文と、人類を護ろうとするこの計画は重要なファクターとなるはずだよ、島くん。
「………」
「ここは、そのための最前線司令室となるのだ」
真田は、改めて彼らの立つ発令所から作戦司令部をぐるりと見渡した。
次郎もつられて、周囲を見回す。
——ここが。そして、俺の計画が。…人類救済に…奏功する——。
「…そうだ。Y計画とは…なんだか、説明していなかったな」
「あ、はい」
「ヤマトのY、ですよ、島さん」
折原が、真田の横からニッコリ笑ってそう言った——
「おいおい、私の台詞を横取りしないでくれ」
「うふふっ」
「ヤマト……?」
最後に投影されたモニタ映像に、次郎は戦慄する……アクエリアス。
それは、氷に閉ざされた墓標、ヤマトの眠るアクエリアス氷塊の映像だった。
「宇宙戦艦ヤマトを、我々は復活させる。人類の『希望』を甦らせるんだ。そして、この人類救済計画の事実上の立案者は君だ……島次郎」
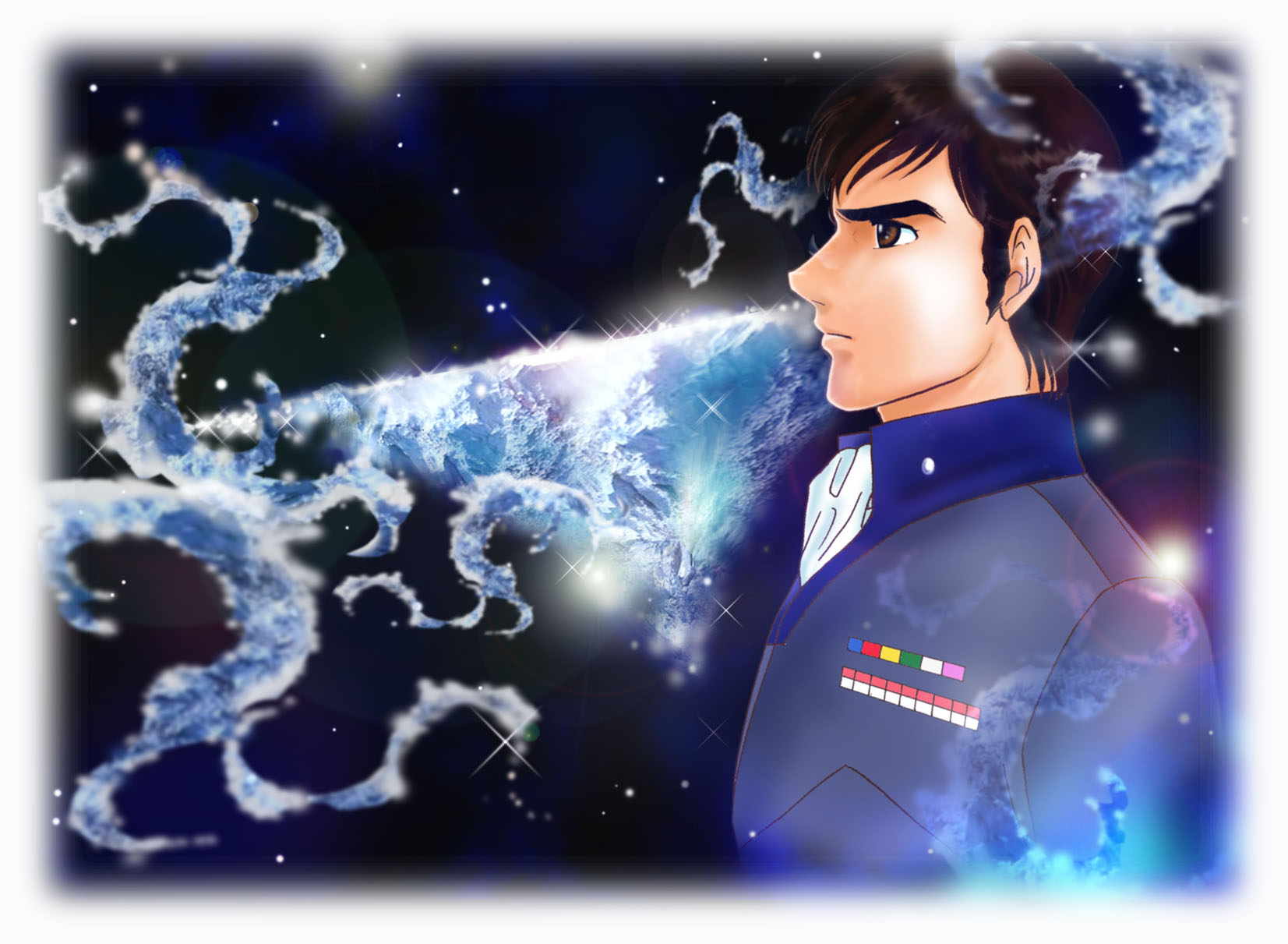
* *********************
第三章「ヤマト復活」(1)へ続く。