**************************************
なあ、一緒になんか食って行かねえ?
夕飯を外で食べて帰らなくてはならない、という勇馬と一緒に、次郎はステーションビルへと足を運んだ。学校帰り、制服で繁華街をうろつくことに未だに抵抗があるなんて…中途半端な反抗精神だな、とちょっと苦笑する。
(母さん、心配するかな)
とことん評判落して、「島大介」の名も失墜させてやりたい…そうは思いながら、母を悲しませることだけはするまい、とどうしても考えてしまうこの思考回路が恨めしい。なあ勇馬、俺んちで夕飯食ってくか?と言いかけて、次郎は幼なじみの視線にふと目を引かれる。
冷めたホットドッグを頬張りながら、勇馬は月を見ていた。
ステーションビルの屋上、子ども向けの乗り物や屋台が並ぶ広場を抜けたところにある、自動販売機しかない閑散とした広場。…その隅のベンチで夜空を見上げ…、勇馬は呟いた。
「……あそこにいるんだよな。お前の兄ちゃん」
「………」
満月から視線を右へ移す……そこにひと際煌めく、歪な塊。水惑星が残した、氷の星……。月明かりに、地上からでもくっきりと輝いて見える、アクエリアスの氷海である。
「次郎、お前さあ。…やっぱ、贅沢だよ。兄ちゃんにいつでも守ってもらってるような気がしないか?」
「あ?」
こいつ、何オトメチックなこと言ってやがる。次郎はムッとした。…俺が一体どんな気持ちで、ずっとあの氷の海を見て来たと思ってんだ。
「…悪趣味だな。毎晩兄貴の墓、見なけりゃならないんだぞ…いい気分なもんかよ」
最初、大変だったんだぞ。親父もお袋も、あれを空に見るたびに黙っちまって。そのうち、夜は外にも出なくなったんだ。——今はようやく…そんなに気にしないでいられるようになったけどな、……残酷だよ。
実際、兄大介が戦死した直後…まだ小学生だった次郎は「どうにかしてあの氷の星へ行き、兄を地球へ連れて帰れないか」と終始考えてばかりいた。
たかが月の近くである。観光船の定期航路もあるし、実際、父の会社の施設の幾つかが月面にあるほどだ。一体なぜ、あんなに近くにある場所へ誰も行こうとしないのだろうか。
防衛軍幹部に昇進した古代や、科学局長官真田を訪ね、真面目に相談を持ちかけたこともあった。しかし、資源輸送のための主要な艦船もなく復興に携わる健康な人員すら不足していた時期である…遺体の捜索だけに傾ける人的余裕も経済的余裕も、当時の地球には皆無だった。古代、そして真田も「それを考えたことがないわけではないんだよ。でもね…」と次郎を諭した。
人類の救いの象徴たる<ヤマト>が眠る氷の海は、地球の誰もが仰ぎ見ることの出来る、文字通り「象徴」として天空に輝くべきだとされ…そのサルベージについては検討する必要性はない、とされた。不可触の神聖な領域として保存すべきだという意識も、そこには働いていたようだ。
いつしか、次郎はそれを諦めた。古代も真田も、子どもの次郎からは容易く連絡を取るのが難しいほど多忙な毎日を送るようになり。夜空にアクエリアスを見上げることにも、次第に苦痛を感じなくなって行った——。
兄ちゃん。…大介兄ちゃんは…本当に、そこにいるのか…?
夜空に煌めく、無言の墓標……次郎は改めて、その星が纏う光を、目を細めつつ…凝視した。
ヤマトの最後が、どんな様子だったのか……次郎は知らない。詳細をもっともよく知っているであろう古代に対しても、それを問いただす勇気はなかった。
急速に凍結する海の中で爆発した船は、どうなるんだろう?第一、戦死した乗組員たちの身体は、奇麗なまま眠っているのだろうか。……中学生の頭でも、それはほとんど望めないだろうと、ある程度分かる。ヤマトそのものだって、粉々になっているかもしれないんだ。その中にいた人なんて、…もっと。
苦しそうに俯いた次郎に気付き、勇馬が慌てる。
「…悪い」
ううん、と首を振った。その次郎を横目で見ながら、勇馬は言い繕うように続けた。
「…俺、親父が田舎で死んでるだろ…。田舎のうちも、近所も全部、遊星爆弾で吹っ飛んだからさ、家も親父の身体も残らなかった。今行ったって、跡形もないんだ。…それに較べたら……いつでも空を見りゃ、そこにいてくれる、って思えるのが、…羨ましかったんだ」
「…羨ましい…?」
「お前の兄ちゃんに較べたら、うちの親父なんか大したことないさ。でもな、親父は軍人じゃなかったけど…すげえ奴だったんだぜ…」
あれは日曜日だった。俺とお袋は、たまたま…出掛けてた。親父は警報が鳴ってから、隣の家の婆ちゃんを助けに戻った。遊星爆弾が落ちるまでに、シェルターから3回、外に出た……3人助けた。まだ外にいる、って言って、4人目を助けに行って……死んだんだって。
一気に言って、は…と苦笑する。
「3人助けたって、お前の兄ちゃんの足元にも及ばねえけどな」
——『ヤマト』が救ったのは、何億、だもん…
「親父の死んだ場所は、もうどこにもない。でもさ、お前は空を見ればいつでも兄ちゃんを思い出せるじゃん」
…忘れるのが、一番…哀しいことだと思ってんだ…俺。
だから。
「羨ましいって…んなこと…な…」
しまった、と息が詰まる。何だよ俺……何、泣いてんだよ——。
「あーあ、次郎、お坊ちゃんだな。泣くなよ…」
「るせえ」
へへへ、と笑った勇馬が、ごほごほ、と咳き込んだ。夜風がちょっと肌寒い…
「なあ、ラーメン食いに行こうぜ、ラーメン」
「おう」
歩き出せば、氷塊が…月と一緒について来る。
——二人は連れ立って、屋上を後にした。
***
だが、その晩…帰宅した次郎を待っていたのは、父の怒号だった。
「そこへ座れ」
それを無視してリビングを出て行こうとした次郎の腕を掴み、父が低い声で唸った。「…何時だと思ってる」
「……うるせえな」「なんだと…もう一度言ってみろ…!」
「お父さん!」
母が悲痛な声で割って入った。「私が後でよく言って聞かせるから。ちゃんと帰って来たんですし、…補導されたわけでもありませんし」
「当然だ。補導なんかされてみろ、いい面汚しだ」
「…ふん、結局それか」
「なに」
次郎は前髪の奥から父を睨みつけた…「兄貴はそんなことしなかった、そう言いたいんだろ!…いつだってそうだ、島大介、島大介……俺を心配してるんじゃない、兄貴の名前を心配してるだけだろうが!」
父が思わず拳を振り上げた。
「…っ…!!」
思わず目をつぶった。殴れるもんなら殴ってみろ、そう言いかけて、次郎はぎょっとする……力なく拳を降ろした父の顔が、奇妙に歪んだのだ。
「……次郎」
歯の間からひと声だけ漏らし…父は俯くと背を向けた……
「すまない」
次郎は何も言わなかった…いや、言えなかった。
涙も後悔も、痛い家族同士庇い合おうとして、それにしくじるのも…もうたくさんだ。
——母が呼び止めるのもかまわず、一目散に二階へと駆け上がる……
「ちくしょう…!」
兄ちゃん。
…大介兄ちゃん…なんで死んだんだよ…!!
暴れるのも、もう飽きた。壁を殴っても…自分の拳が痛いだけだ。本棚を倒しても、散らばった本を片付けるのは自分。女子じゃあるまいし、と自嘲する…ベッドに突っ伏してただ泣きじゃくるのが、結果的に一番落ち着くだなんて。部屋の照明を点けなければ、窓に浮かぶあの氷塊が、また否応無く目に入る……かといって照明を点ければこの惨めな自分の姿がくっきり見えてしまうから。
次郎はカーテンを締め切った暗い部屋の中で、枕に突っ伏したまま…声を殺して泣いた。
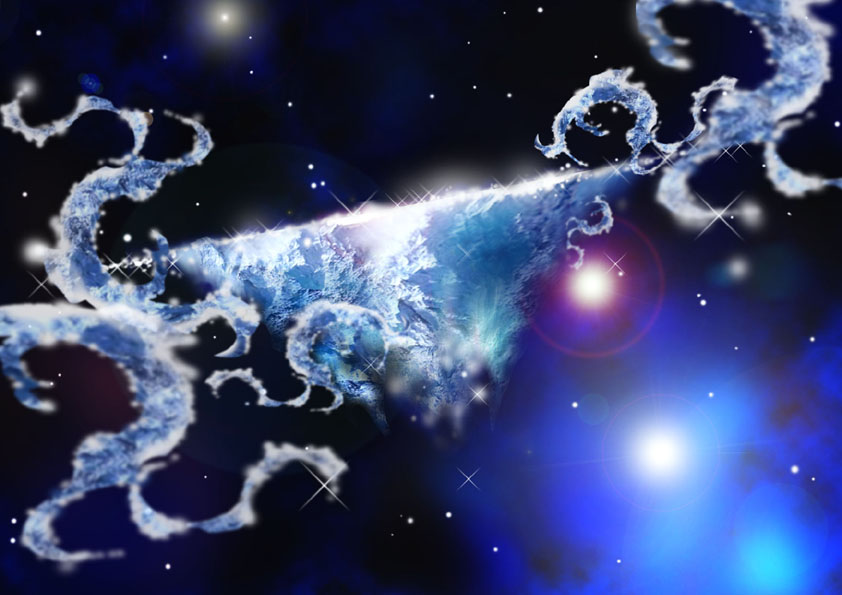
メガロポリスの港を一望できる丘の上。
海風が心地良く吹き付ける岬に造られた、戦没者記念公園——海に面したその公園には、「英雄の丘」と名付けられた小高い一角がある。
「パーパ、はーやく!」
おぼつかない足取りで、しかし驚くほど速く…3つになる娘が走って行くのを、古代進は笑いながら追いかける。英雄の丘に登るには、丘の上の遊歩道からさらに石段を20ほど、上がらなくてはならない。途中に幅の広い踊り場が2ヶ所設けられているが、美雪は休みなく段を駆け上がり、頂上に立って父親を振り帰ると万歳!をした。
「ゆき、いっちばーん」
「美雪、気を付けろよ…!!」
「あーい」
言っている傍から、ぺしゃん、と後ろへ尻もち。
「うわ…!!」前のめりに転ばなくて、ホンットに良かった…!
妻の雪が毎朝丁寧に梳かす、腰までとどく艶やかな黒髪が、くるんと波打って跳ね起きる。この娘が、「転んで」泣いたところを未だに進は見たことがない。
「お、…やっぱり強いなあ、美雪は」
「えへへー」
石段を上がり切り、その小さな頭にポン、と手を乗せ…古代進はにっこり笑った。
「あー…、ぼーゆう」
ぼーゆう??
美雪はどうも女の子にしては言葉が遅い。最近ようやく、劇的に単語が増えて来たのはいいが、語彙よりも「なに?」「どちて?」の方が圧倒的に多いのが玉にきず、である……
「なんだい、ぼーゆう、って…」
美雪の指差した方を見る。たんたんたん…と転がって来たサッカーボールに、ああ、と合点した。なんだ?ここでボール遊びか、いかんな…どこの子だ?
そう思い、周囲を見渡した古代の目に入ったのは、見覚えのある…少年だった。
「次郎くんか…?!」
(3)へ