
花の香りがしたように思って、テレサは目を開けた。
ベッドの上に起き上がろうとしたが、酷い目眩に襲われる。ゆっくりと半身を起こしてベッドサイドのテーブルを見ると、その上に何か白い布が畳んでおいてあるのが目に入った。……白い布は、服……丈の長いドレスだ。部屋の窓にはカーテンが引かれていたが、外は明るく、日ざしがその隙間からキラキラとこぼれている。
目眩がおさまるのを待って、テレサはドレスに手を伸ばした。今着ているのは、ピンク色のストンとした寝巻きだ。着替えてから、この部屋の外に出るべきだと、漠然と思う。
白いドレスはすっかり痩せてしまった彼女の身体を優しく包んでくれた。ここの主人が毎日用意してくれる素朴な質感のドレスだが、膨らんだ袖や華奢なレース使いがとても愛らしい。ふと気がつくと、サイドテーブルの上には着替えの他に、小さな手鏡と柄に飾りの宝石が付いたブラシも置いてある……
テレサは鏡をとって、覗き込んだ。
(………酷い顔)
血の気の無い頬、青い唇。まるで死人みたいだわ……溜め息をつき、鏡を伏せた。仕方なくブラシで髪を梳いてみる。確か…昨日も誰かに聞いた覚えがあったのだけれど、……ここはどこなのだろう…?一体、今はいつなのだろう…?
そんなことさえも覚えていられないほど、テレサの記憶はひどく欠けてしまっていた。
ドレスに着替えてベッドから立ち上がり、おぼつかない足取りで窓を開け、庭に出る。眩しいだろうと思ったが、日射しはそれほど強くない。
(………いい匂い…)
不思議な香りのする空気を、胸いっぱいに吸い込む。
人工的に刈り揃えられた芝や灌木の間に、白く滑らかな大理石のタイルで作られた小さな通路が見える。その先に進んで行くと、小さな噴水とそれをぐるりと取り囲むように、赤い小さな花の咲き揃った花壇があった。
花壇のそばに置かれたガーデンチェアに、そっと腰かける。
可憐な赤い花を見ていると、それが自分に語りかけて来るように感じる。この花の名前は…ユキ。なぜだろう、そんな風に思うのは。
上を仰ぎ見ると、外だと思ったこの場所は、高い天窓のある大きなサンルームだった。たった十メートル程度を歩いただけなのに、息は切れ、動悸がする……テレサはほう、と息を吐いた。
「……やあ、おはよう」
背後から男の声がした。振り向くと、見覚えのある黒い髪の、長身のほっそりした男性が灌木の間の通路に立っていた。
「……おはようごさいます…」
「よく歩行器なしでここまできたね。今日は調子がいいんだね」
彼は白いスーツを着ていた…羽織っているマントも純白で、清潔な印象を与える。褐色の頬がにっこり微笑んでいた。
…この人は……、ええと、…ウォード…先生……
お医者さま。
そう、彼は医者だった。
一日のうち、比較的意識がはっきりするのが手足のリハビリの時間だった。酷い痛みを伴うリハビリの最中、この医師はずっと労りの言葉をかけてくれ、励ましてくれた。テレサは彼に全幅の信頼を寄せるようになったが、あいにくと記憶の方はなかなか元に戻らなかった。
小さい頃の事は断片的に思い出すことが出来るのだが、その後自分がどこにいて、何をしていたのかがわからない。ただ、そうして記憶の糸をたぐっていくと、恐ろしく凄まじいイメージが甦る一瞬がある。思い出すと身体が震えるその記憶は、目も眩むような光芒と灼けつくような火傷の痛み、そして「反物質」…という言葉と共にあった。「彗星帝国ガトランティス」、それも、一緒に思い出した国の名だった。
そしてもう一つ。忘れられない人の名がある。
ウォードの、黒い髪を見ると思い出す……同じ黒髪の、優しい目の人。
名前は、…シマ——
なぜその名を思い出すと涙が溢れ出してしまうのか。そしてなぜ、涙とともに、胸が熱くなるのか…?自分は彼を、何かから助けたい…と強く願っていた、それは憶えている。
——でも、一体なぜ?
そこまで考えると、ふいにズキンと頭痛が走る。いつもそうだ。彼にまつわる一連の出来事を考える度、身体が警告を発するような気がして、彼女の思索の糸は断たれるのだった。そもそもその出来事がいつのことなのかすらも…解らない。
「…すみません…今日は、何日ですか」
それで毎日、こう聞いているような気がしてテレサはちょっと気が引ける。だが、ウォードはいつも丁寧に応えてくれるのだった。
「ガルマン・ガミラスの暦ではG・D紀元8年、6月18日だ」
「6月18日」
ウォードは頷いてにっこり笑った。「朝食は食べた?奥のテーブルに用意させてあったはずだが」
「あ」…それは気付かなかった。まっすぐにここへ出て来てしまったから。
「…じゃあ、戻ってまず朝食をとらないとね。一緒に行こう」
手を差し伸べたウォードに、テレサははい、と頷いた。「…あの」
医師はなんだい?と言いつつ優しく彼女の手を取る。
「…素敵なドレスを…ありがとうございます」
アレス・ウォードはそれを聞いて、声を立てて笑った。「…昨日もまったく同じことを言ったね。いいんだよ、それは全部総統からの贈り物なのだから」
「…そう…とう…?」
少しずつ思い出せばいいよ、と微笑むウォードの腕にすがり、テレサはゆっくりと部屋へ歩いて行った。
テレサにとって、この医師と過ごす時間は心地よいものだった。時折、このまま過去のことなど何も思い出す必要はないのではないか…とさえ感じた。
だが、体力の回復とともに彼女の記憶は徐々に甦って行った。「反物質」「彗星帝国ガトランティス」…そして「島大介」「ヤマト」…。
時に恐怖と畏怖の念、時に燃え上がるような恋情と思慕の念……それらが統合されて彼女の記憶に甦るのに、そう時間はかからなかった。
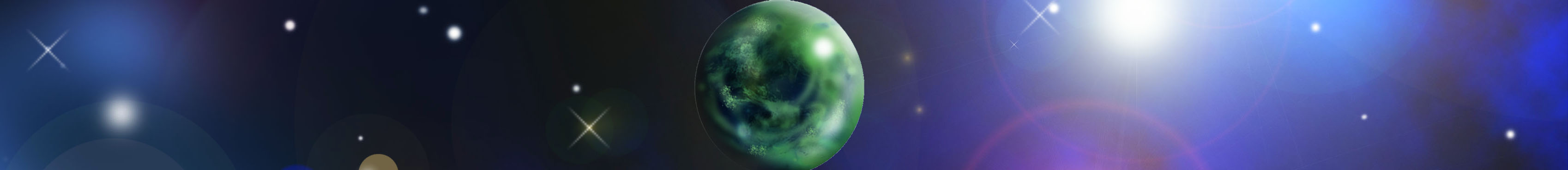
「…テレサ?」
ある晩のこと——
アレスが診察のために総統府に誂えられた彼女の部屋にやってきたところ、その姿が見当たらなかった。彼女が好んで時間を過ごす、温室の噴水のそばにもいない……
その日は、ガルマン・ガミラスの建国記念日だった。日中から総統府の周囲は祭りを祝う人々の喧噪で包まれており…ほど遠くない場所に位置する宇宙港ではデスラーの名を戴く大艦隊が、観閲式典のために祝砲を絶え間なく打ち上げていた。数時間にも及ぶ祝砲の轟は戦場を彷彿とさせたが、その号砲は国の興隆への賛辞である。その音に怯え震える者がいることなど、誰一人気付きもしないのだった。
テレサはフロアの反対側にある、建物の周囲の湖を望む真っ暗なバルコニーの隅に、頭を抱えて踞っていた。
祭りの続く宇宙港からは建国を讃える光芒が盛んに打ち上げられており、夜空は絶え間なく閃く雷鳴に明るく彩られている。
「…どうしたの、こんなところで」
片膝を付き、彼女に話しかけたアレスはぎょっとした。
彼の声にゆっくりを顔を上げたテレサの目には、恐怖と絶望の色が浮かんでおり……その顔は涙で濡れていた。蒼白な唇が震えている…。
「……私は……滅ぼしました…彼らを…」
聞き取れないほどの微かな声で、テレサは呟いた。「反物質…テレザリアムから解放して……」その目は、アレスを見てはいなかった。
——思い出したのか。
デスラーからは、7年ほど前、テレサが土壇場で地球と白色彗星帝国との闘いに介入し、自らその能力を使って彗星帝国を壊滅させた、と聞かされていた。
だが、それがなぜだったのか…、そこまでは彼女本人以外、誰にも解らない。総統からはその理由も解明するようにと要請を受けている。
頭上に、デスラー艦隊の打ち上げる巨大な焔の輪が上がる。同時にテレサは「ああ…っ」と叫び声を漏らし、頭を抱え再び身体を固くした。
夜空に無数の祝砲の火花を仰いだ一瞬後、バルコニーは闇に落込む……
「…テレサ」
アレスは彼女の両肩に腕を回し、立ち上がらせようとした。とにかくここから部屋へ連れて戻らねば。
——と、その瞬間——
「島さん」
次の祝砲が、アレスの顔を白く照らし。それを見上げたテレサが、悲痛な声で彼をそう呼んだのだ。
「島さん……島さん…!!」
驚くほどの腕の強さで、テレサはアレスの胸にすがりつき、慟哭した。
医師として、患者の記憶が戻った瞬間に何をするべきか、アレスは思わず失念していた。私は島じゃない。その名で私を呼ぶのは止めてくれ…!
しかしその意志とは裏腹に、アレスはテレサに熱い抱擁で応えていた。彼女は怒濤のような記憶の上潮の流れに我を忘れている…テレサがその意識の中で抱きしめているのは「島」だとしても。その指が、腕がこの身に縋り付き応えを求めていることを、計らずも幸福に感じる自分がいた。声には出さず、アレスはテレサの耳元で囁いた……「テレサ…愛している…」そしてその華奢な体躯を強く抱きしめた。
テレサは不規則な呼吸を続けていたが、急に安心したようにほう…と深く息を吐いた。1・2度彼の頭を両手で愛し気にかきしだくと、その腕からふ、と力が抜ける。身体は急激に弛緩し、ぐらりと頭を垂れた。
「…お願い…生きて……わたしの…いの…ち…」
アレスは唐突に悟った。
彼女はあの男…島を救うために、ガトランティスを滅ぼしたのだ——。
医師に身体を預け、気を失ったテレサは心なしか幸せそうに微笑んでいた。
(15)へ 「奇跡」Contentsへ